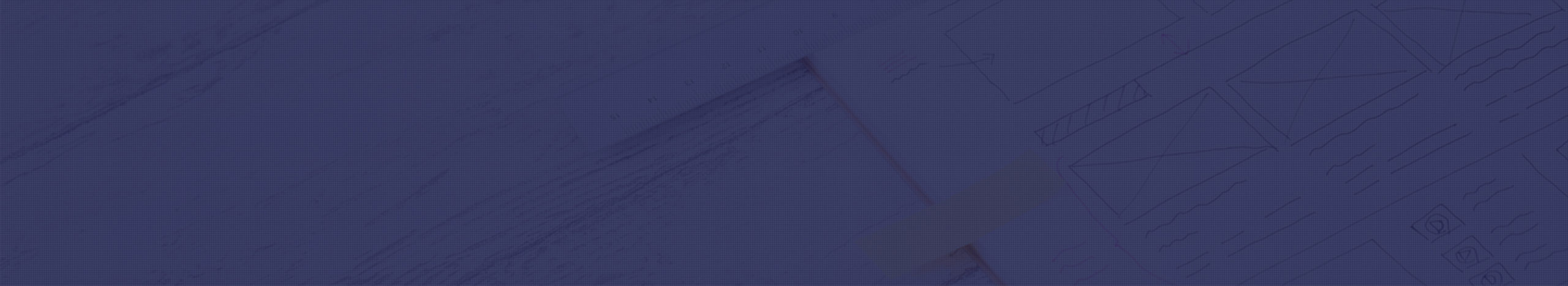
NEWS
最新情報
- 会計税務顧問
消費税の申告って、どういう仕組みで計算されているの?

売上が上がると、事業規模とともに大きくなっていくのが消費税の支払。最初は消費税の支払が免除されるところからスタートしますが、売上が1,000万円を超えると免除されなくなり、5,000万円を超えると簡易課税制度が使えなくなり、5億円を超えるか課税売上割合が95%未満になると、支払った消費税が全額は控除できないというルールが適用。
売上規模が大きくなるにつれ仕入に係る消費税(仕入控除税額)は控除できる割合が少なくなります。
今回はこの中で売上が5億円超えまたは課税売上割合が95%未満になった場合の、消費税の計算方法をお伝えしていきます。
消費税率の引き上げを控えていますので、自社が支払う消費税が適正か。今一度確認しましょう。
Contents
課税売上割合の計算方法って何?
冒頭に『売上が5億円を超えるか課税売上割合が95%未満』とありましたが、そもそもこの『課税売上割合』とはなんでしょうか?
課税売上割合とは、売上全体に占める課税売上の割合を言います。
例えば、国内で商品(課税売上)を税抜7億円、土地(非課税売上)を3億円で売却した場合、
課税売上割合は
7億円 / 7億円 + 3億円 = 70%
となります。
なお、海外へ商品等を輸出して販売した場合は『輸出免税売上』として課税売上(分子)に入りますので気を付けてください。
式にするとこういうイメージになります。
(他にも『非課税資産の輸出等』という分類もありますが、該当するケースがほぼないため省略しています)
土地を売却したり賃貸経営を始めたりすると非課税売上げが多くなり、課税売上割合が95%未満になるケースも出てきます。
十分に気を付けましょう。
仕入控除税額の個別対応方式と一括比例配分方式って何が違うの?
売上が5億円を超えるか課税売上割合が95%未満の場合、支払った消費税全額が控除されないことは冒頭でもお伝えしました。では、控除できる消費税の金額はどのように計算すればいいのでしょうか。
この場合の仕入控除税額(差し引ける消費税)の計算は、『個別対応方式』か『一括比例配分方式』を使わなければなりません。それぞれの計算方法をざっくりまず説明します。
個別対応方式
それぞれの仕入がどの売上に対応するかで消費税の控除額が変わります。
1.課税売上にのみ対応するもの
(商品や原料の仕入・店舗の家賃など)
⇒全額を差し引けます。
2.課税売上と非課税売上に共通して対応するもの
(交際費や事務所の家賃など)
⇒消費税額×課税売上割合の金額だけ差し引けます。
3.非課税売上にのみ対応するもの
(住宅の賃貸に係る管理手数料、土地の仲介手数料など)
⇒差し引けません。
1と2の合計額が仕入控除税額(差し引ける消費税)となります。
一括比例配分方式
支払った消費税額の総額×課税売上割合の金額が、
仕入控除税額(差し引ける消費税額)となります。
ですので、非課税売上がほとんどない事業者であれば、
課税売上に対応する消費税を全額控除できる個別対応方式の方が有利です。
ただ、不動産業者や医者などの非課税売上が多い事業者であれば、
土地の売却や保険診療などの非課税売上に対応する仕入や経費が多くなりますので、
一括比例配分方式の方が有利になる場合もあります。
実務ではそれぞれの支払がどの売上に対応しているかを1つ1つ判定しなければどちらが有利かの判定もできませんので、
日頃から集計とチェックをこまめにしておきましょう。
なお、一括比例配分方式を採用した場合、2年間の強制適用があります。
次年度も含めてどちらが有利になるかまで検討しましょう。
課税売上割合に準ずる割合ってどういうこと?
普段は非課税売上のほとんどない事業者が、たまたま土地を売ったなどでその年度だけ課税売上割合が大きく下がることもあります。
この場合、何もしないと仕入控除税額(差し引ける消費税額)が少なくなります。
例えば、共通する仕入の消費税額が1,000万円だった場合、
1.普段の課税売上割合が90%
1,000万円 × 90% = 900万円の控除
2.土地の売却で課税売上割合が60%にまで下がった
1,000万円 × 60% = 600万円の控除
土地を売却しただけで300万円も多くの消費税を払わなければいけないこととなります。
でも、たまたま土地を売っただけでこうなるのは納得がいかないですよね。
このようなケースの時に使えるのが、『課税売上割合に準ずる割合』です。
”土地を売ったのはイレギュラーケース”で、
”普段の課税売上割合とはかけ離れている”から、
”いつもの課税売上割合で計算をさせてください”
と税務署にお願いして通常の課税売上割合とは違う割合を適用させるのが、課税売上割合に準ずる割合です。
『課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書を税務署』へ提出し、承認が下りればいつもの課税売上割合を使って計算することができます。
ここで注意点が2つあります。
1.早めに提出すること。
承認までには時間がかかるため、期末ギリギリの提出では間に合わない可能性があります。
2.課税売上に準ずる割合を使わなくなったら、『課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書』を提出すること。
先ほどの土地の例などはその年だけのケースになるため、次の年度では通常の課税売上割合でよいこととなります。ですので、取消しの届出を忘れずにしましょう。
あまりお目にかかることのない制度ですが、使い方によっては消費税の納付額を大きく抑えることができますので、ぜひ押さえておきましょう。
課税売上割合が著しく変動したときの調整はどうするの?
課税売上割合が著しく変動したときには、一昨年に購入した100万円以上の資産については消費税額を調整しなければなりません。(個別対応方式で課税売上と非課税売上に共通して対応する仕入れで消費税を計算したか、
一括比例配分方式で消費税を計算したときに限ります)
例として、各年度の課税売上割合が
一昨年 40%
去年 80%
今年 90%で、
一昨年に1,080万円(税込)の建物を購入したとしましょう。
この場合、一昨年に計算した消費税額は
1,080万円 × 8 / 108 × 40% = 32万円
となります。
ところが、今年購入していれば
1,080万円 × 8 / 108 × 90% = 72万円
となり、差し引ける消費税額に40万円もの差が出てしまうのです。
これを適正な金額に調整しましょうというのが
課税売上割合が著しく変動した場合の調整です。
この調整は、
1.調整の対象となる固定資産があるか
2.著しい変動に該当するか
の2つに当てはまるときに、その税額を計算し、調整を行います。
1.調整対象となる固定資産があるか
これは一昨年の年度に100万円以上(税抜)の固定資産を購入していれば該当します。今回のケースでは1,080万円(税込)→1,000万円(税抜)の建物を購入しているため、該当します。
個別対応方式で課税売上にのみ対応する仕入れの場合、すでに消費税額の全額を控除済ですので、対象外となる点にはご注意ください。
2.著しい変動に該当するか
これは『変動差が5%以上』かつ『変動率が50%以上』の時に該当します。
・変動差
一昨年の課税売上割合 - 通算課税売上割合 ≧ 5%以上
または
通算課税売上割合 - 一昨年の課税売上割合 ≧ 5%以上
・変動率
変動差 / 一昨年の課税売上割合 ≧ 50%以上
※通算課税売上割合は過去3年の事業年度にわたる課税売上割合です
今回のケースでは
通算課税売上割合
(40% + 80% + 90%) / 3 = 70%
変動差
70% - 40% = 30% ≧ 5%
変動率
30% / 40% = 75% ≧ 50%
となり、著しい変動に該当します。
それでは、調整税額がいくらになるか計算してみましょう。
調整税額は
通算課税売上割合で計算した消費税額 - 一昨年に控除した消費税額
です。
今回の例をあてはめると
・通算課税売上割合で計算した消費税額
1,080万円 × 8 / 108 × 70% = 56万円
・一昨年に控除した消費税額
1,080万円 × 8 / 108 × 40% = 32万円
・調整税額
56万円 - 32万円 = 24万円
と、24万円消費税額が安くなります。
ここで注意しなければならないのが、消費税額が高くなるパターン。今回のケースでは一昨年の課税売上割合が40%で今年が90%の為安くなりましたが、逆に一昨年が90%で今年が40%の場合は消費税額が高くなり、この申告を忘れていると追加での納付+延滞税などのペナルティがあります。
税務署からはこのあたりも厳しく見られますので、申告漏れの内容に十分気を付けましょう。
今回は課税売上割合に関する話をしていきましたが、その道のプロでも迷うことがあるくらい難しい論点でもあります。
わたしは常に迷っています(苦笑)
また、納付する金額が大きく変わる場合もありますので、不安な点があれば、税務署や税理士などの専門家に問い合わせした方が安心でしょう。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 税理士変更2019.07.25税理士を変更したい。よくある理由と注意すべきポイント
税理士変更2019.07.25税理士を変更したい。よくある理由と注意すべきポイント 青色事業専従者給与2018.12.11配偶者(妻・夫)が事業を手伝うなら青色事業専従者給与を活用しよう。
青色事業専従者給与2018.12.11配偶者(妻・夫)が事業を手伝うなら青色事業専従者給与を活用しよう。 大阪たこ焼き2018.07.25大阪のたこ焼き売店が1億3,000万円を脱税。飲食店の税務調査について税理士が解説。
大阪たこ焼き2018.07.25大阪のたこ焼き売店が1億3,000万円を脱税。飲食店の税務調査について税理士が解説。 事業承継2018.07.20事業承継に使える組織再編⑤「株式移転」を税理士が解説
事業承継2018.07.20事業承継に使える組織再編⑤「株式移転」を税理士が解説





